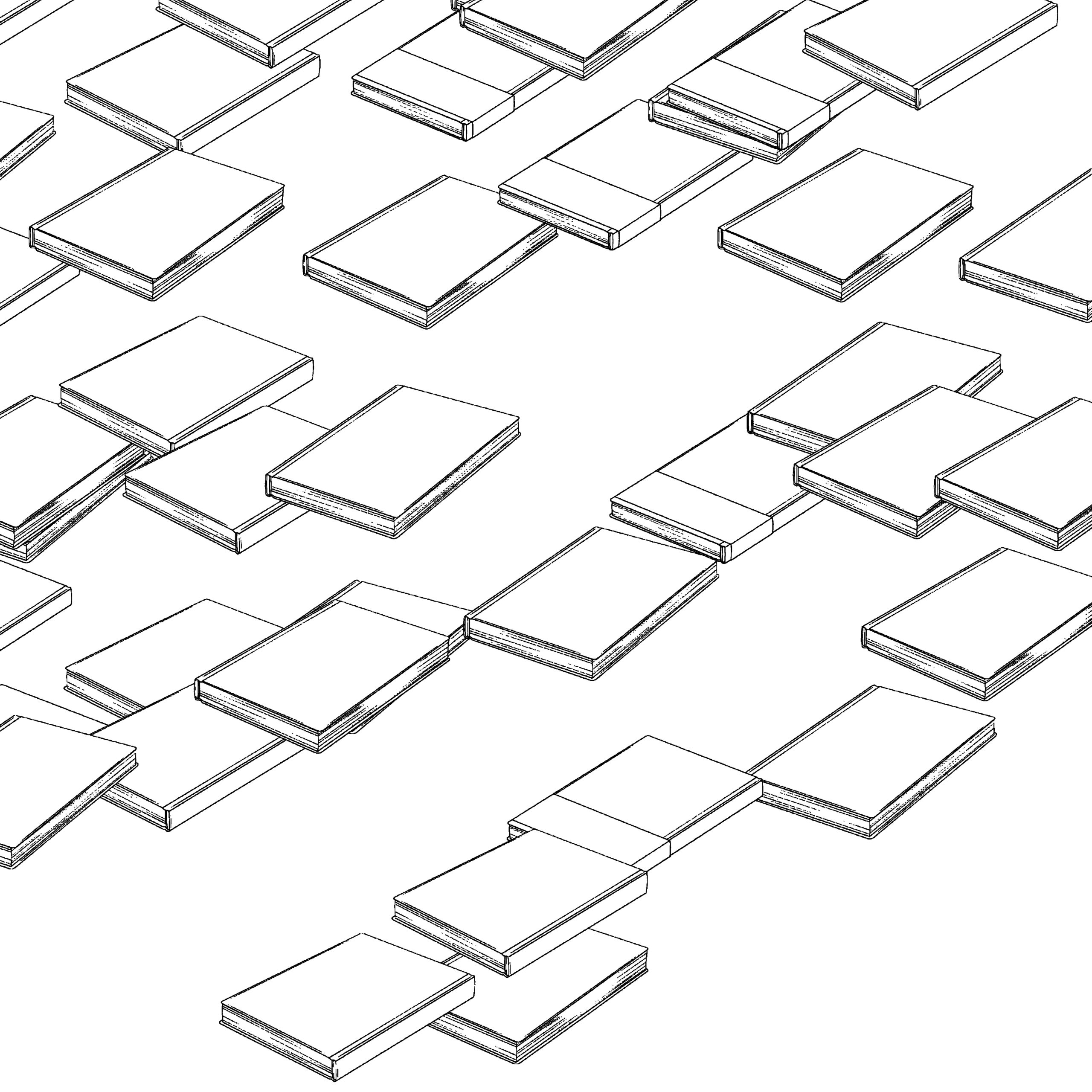二、彼方のそと
一
ぱあん、と小気味の良い音がして木刀が道場の床を滑っていく。小手を打たれた長谷部は上段に構えていた腕をそのままに二度瞬きしたが、やがて静かに腕を下ろした。ゆっくりとぎこちない様子で手首を回している。筋を痛めたり骨を折ったりするようなことは無かったようだ。
「また負けた」
「……だが、一本重ねる度に動きが変わっている、と思う。覚えが早いな」
「そうか、やはり場数は大事だな」
ぐるぐると手首がよく回るようになると、服で手のひらの汗を拭いつつ長谷部はまた木刀を拾いに行った。さすがは『特別元気』などあだ名されるほどはある。表情こそいつもと変わらぬぼんやりした顔のままなのだが、その背中に底知れぬ負けん気を感じて山姥切は慄いた。手合わせを始めてから十本はとうに取っているが、気持ちの面ではやや圧されつつある。
「……ひょっとして勝つまでやる気じゃないだろうな」
「もちろんだ」
相変わらず気持ち良いほどの即答だ。どう控えめに見ても何も考えていない。
山姥切は元の本丸では初期刀と並んで高い錬度を誇っていた。どの出陣先でも傷を殆ど負わなくなっていたし、極めた短刀たちとの手合わせも難なくこなせていた。策もなく真っ向勝負で今の長谷部が山姥切を打ち負かすことができる可能性と問われれば──閉口するほかない。
「……もちろんだじゃないんだが……お前、特も付いてないだろう」
「とく。徳か。確かにお前ほどは積んでないとは思うが、お前の強さに関係があるのか?」
「……何の話だ」
腕を組み首をわずかに傾げている長谷部は真顔だ。無論、ふざけているつもりもないのだろう。一体どんな本丸から追い出されたらこんなことになってしまうのだろうか。何とも言えない複雑な気持ちを抱えつつ構えを取る。夕餉くらいまでなら付き合ってもいい。たまに繰り出す突飛な行動で不意を突かれて一本二本取られるかもしれない。戦に絶対はないのだ。絶対があるのなら、山姥切はこの本丸に流れ着いてこの長谷部と向かい合ってなどいない。
腕を上げて構えると、長谷部もそれに応じる。どこか目が炯々と光っているのは、梅雨の晴れ間が道場の物見窓から光を差し込んでいるからだろうか。どちらともなくいざ打ち合おうとした時、とたとたと軽快な足音がふたつ近づいて来たのを耳が拾った。
「お、ツッコミと元気じゃん!」
「ほんとだ」
終日開け放たれている道場の戸から顔を覗かせたのは加州と大和守だ。様々な本丸から同じ名を持つ刀が複数逗留しているのも珍しくないのがこの『清めの本丸』だが、二振は同じ本丸から療養に来ている。
この本丸には神刀や霊刀と呼ばれる刀が他の本丸よりも多く属しており、戦の中で刀傷に留まらぬ穢れや呪いを受けてしまった刀を一時的に預かって癒しているらしい。一足早く復調し本丸内の仕事を無理のない程度に手伝っていた加州に続いて、大和守も全快しつつあるようだった。久々に刀を振りたくなったに違いない。
「……それはやめろと」
「えー?でもピッタリでしょ?これ以上のあだ名ないって」
「俺はただの元気じゃないぞ。『特別元気』な長谷部だ」
「うんうん、そーだった。長谷部は今日も特別元気でえらいえらい」
長谷部と加州とでは見上げるほどの身長差があるが、手を伸ばして頭を撫でる加州に、長谷部は表情ひとつ変えずにされるがままだ。つい先ほどまで勝負に対する底知れぬ執念を見せつけられていただけに、山姥切はなんとも言えない複雑な気持ちを噛み締めた。なんとなく前髪にかかる布をいじってみたりする。
「丁度良かったよ、やっとだるい感じも無くなってきたからさ、体動かしたいとこだったんだよね」
ぐるぐると肩を回しながら、大和守が壁に掛かった木刀を吟味し始めた。加州と手合わせを始めるのだろうとばかり思っていたが、すぐに己の刀身と近いものを見つけてきたらしい大和守はその切っ先を山姥切にまっすぐに向けた。
「僕に勝ったら、あだ名変えてもいいよ」
「……その前にあだ名を付けるのをやめてほしいんだが……」
「じゃあ安定に勝ったら改名、俺に勝ったらあだ名は無しってのは?」
「それはそれで清光がラスボスっぽくてちょっとなあ」
わざとらしく不服そうな表情を作ってみせる大和守に対し、考えすぎだってと加州は愉快げに笑っている。どこの本丸でも大抵この二振の仲は良いものらしい。仕方なく大和守に対峙すると、異を唱えたのは放り出された形になった長谷部だ。
「待て、俺がまだ山姥切に勝ってないぞ」
「大丈夫だってえ、俺がツッコミに勝って、その後お前が俺を倒せばあいつ倒したことになるでしょ?」
「なるほど」
「……なるほどじゃない」
「だから長谷部は俺を応援してよね!」
「分かった」
「……分かったじゃない」
「ほらあ、やっぱりツッコミじゃーん!」
この、なんとも言えない承服できない気持ちは一体何なのだろうか。とりあえずできるだけ早く一本決めて不本意なあだ名だけは取り下げさせたい。刀をまっすぐに大和守へと据える。先ほどまでの余裕を見ても分かっていたが、この二振もそれなりの手練れだ。ぴん、と道場内の空気が張り詰める。
「盛り上がっておいでのようだ」
集中していただけに、気配なく闖入した新たな声に思わず飛び上がったのは山姥切だけではあるまい。批難を少なからず込めた目で入り口に目をやれば、一期一振がにこやかに道場を覗き込んでいる。
「ですが、大和守殿は床払いしたばかりですからな。程々に」
「わ、分かってるよ」
「あー…相変わらずここの一期って心臓に悪いよな」
「ははは、お褒めに預かり光栄ですな」
加州がしきりに目配せを送ってくるが、これ以上あだ名の定着は避けたい。山姥切は無言を貫いて目を逸らすに留まった。
「……一期も手合わせかな?一緒にやっていくかい?」
「大和守殿……!?」
話題を変えるためだろう、軽く声をかけた大和守に一期は目を見開き、口元を白手袋の右手で覆い、過剰に反応している。深く考えての言葉ではなかったに違いない大和守は困惑の表情を浮かべてそれをただ見つめている。
「まさか貴方がそのようなことを仰るとは……!私に浮気をしろと仰る」
「……えっと」
「私のこの両手はただ我がつまのためにあるんです。例え木刀と雖も握る気はせん」
「……じゃあ何しに来たんだ」
「いえなに、力の有り余っている方に丁度いい運動がありまして。ご紹介をと」
先ほどまでの驚愕の表情が嘘のような爽やかで柔らかい笑みだ。それが余計に胡散臭い。何かまた頼まれ事を押し付ける気なのだろう。山姥切は加州、大和守と苦い顔を見合わせた。
「僕、あの刀ちょっと苦手。うちの一期さんと全然違う」
「いや、得意なやつ居ないでしょ」
「『つま』の三日月なら得意なんじゃないか……知らないが」
「ははは、さすが山姥切殿。よく分かっておいでですな」
げ、と間抜けな声を出さなかったことを褒めてほしい。極力潜めていたはずの声まで筒抜けらしい。腰元に佩く三日月宗近を柔らかな手つきで撫でる一期からなんとなく三振とも一歩後退する。戦略的撤退、という言葉はこういう時に使いたくなるものらしい。しかしその中でただ一振、長谷部だけはなんの衒いもなく一期へと近づいた。止める間もない。
「おや、長谷部殿。どうしましたか」
「山姥切に勝てなくてな。俺には徳が足りないようだ」
一期は目を丸め、長谷部の言葉を吟味しているようだった。相手の言葉を正しく理解しようとする様だけは、「一期一振らしい」ようにも見える。白い手袋に包まれた指先を顎につけ、一期はわずかに笑みの種類を柔和なものに変えた。
「長谷部殿はどうして強くなりたいんでしょうか。強くなった先に、何がありますか」
ちらり、と目を横に送れば四つの瞳もこちらを見ている。そんなことは問われるまでもないことだ。陽の気を帯びた刀の付喪神として長い時を渡り、思いがけぬ運命で肉体を得た今、己を鍛え、振るい、敵に突き立て、「所有者」のために役立ちたいと考えるのは刀剣男士の本能のようなものだろう。へし切長谷部だって同じはずだ。山姥切の居た本丸の長谷部なら間髪を入れず主のためだと答えるだろう。
しかしこの長谷部は答えない。ただ沈黙が道場を占める。物見窓から差す陽が道場の塵芥をきらきらと照らす音すら耳に入りそうだ。心配になって声をかけそうになったところで長谷部はやっと口を開いた。
「分からない」
はっきりした声だった。迷いや弱さは感じない。しかし長谷部には「主が出て行けというので本丸を出た」という本人談の経歴があるのだ。山姥切の本丸の長谷部のように「主のため」を断言しない。できないのだろうか。再び視線を横に流せば、痛ましげな目が四つ返る。しかし一期は笑みのまま表情を変えていないように見えた。
「……貴方は素直な方ですな」
「悪いのか」
「いいえ」
いいえ、決して。一期は笑みを深めて踵を返す。
「ちょうど頼まれ事をされております。貴方にもお手伝い頂く。きっとよい鍛錬になるでしょう」
「ああ、分かった」
長谷部の返事は気軽なものだが、一期の去った道場内に深いため息が三つ重なった。
三
昼間に土が蓄えたむっとした熱気を足先で掘り返しながら暗闇の中を疾る。夜戦は好きだ。闇の中では美も醜も真も偽もない。ただ勝敗がそこに転がるだけだ。勢い良く向かってくる黒い影を布一枚でかわし、見えた背に刃を走らせる。しかし敵は堪えた様子も無く大口を開けて笑いながら身を翻した。夜戦と違うのは、この敵はただの刃では傷つけることができないことだ。
「鬼退治なんて俺の仕事じゃない……」
敵の刀はその手に無く、ぼさぼさと水気の無い長い黒髪を両手で掴んでいる。遡行軍とはまた種類の違う異形だ。清浄で安全なはずのこの本丸にこの女鬼が度々現れることを知っているのも、その不穏な気配を湿った雨の匂いの隙間から感じ取れるのもどうやら今のところ山姥切だけらしい。石切丸などが慌てて飛び出してきてもおかしくないと思うのだが、今まで助太刀に刀が飛び出してくることは一度もなかった──
「……笑うな」
隣で肩を揺らしている男以外には。どうやら山姥切の独り言を盛大に笑っているらしいが、何故だか山姥切の耳にはこの男の声はひとつも入ってこないのだ。闇夜に紛れても艶を持って光る髪、ゆらゆら揺れる金糸の飾り紐、笑みに細める瞳の奥で浮き沈みする三日月型の打除け。非の打ち所の見つからない立ち姿──三日月宗近である。
しかしその男がざらりと鞘から抜いて見せるのは自身の刀ではない。蒼く淡い燐光で闇夜に型抜かれたその抜き身は紛う方なく一期一振だ。深く息を吸い、それを腰元に引き付けるように中段に構え、力強く水平に凪ぐ。すっぱりと胴を分断された女鬼は、それでも気味の悪い笑い声を立てながら腕を前へ前へと伸ばし──やがて闇夜に溶けて消えてしまった。かちん、と一期一振の鍔が鳴って鞘にその身が収められたことを知る。
女鬼がもがきながら腕を伸ばしていた先に目をやり、山姥切は小さくため息を吐いた。庭の隅、暗闇の中でぼんやりと薄明かりを放つ小さな離れがそこに佇む。塗籠の土壁で、いかにも頑丈な造りは蔵にも見える。不意に現れる女鬼は、いつも必ずここを目指しているようだった。
三日月は細い月の頼りない明かりに笑みをなぞられながら、ゆっくりと離れへと歩み寄った。小さな濡れ縁に腰を下ろし、細く開いた障子を少し押し広げた。かすかに耳が拾っていたすすり泣きの音が強くなる。履物からそっと足を抜き、慣れた様子で部屋の奥へと入っていく。その隅でうずくまる女の背に手を当て、優しい手つきで撫でてやるのだ。これまで幾度も見た光景だった。審神者と思われるその女が決して手放さない一振の刀の残骸と、それを隠す鮫皮の鞘と対面するのもはや幾度目か。だというのに山姥切はそれをいつも直視することができない。布を引き下げて縁側に腰を下ろし、何も見ないようにして女の泣き声を背でただ聞いていた。
やがてそれが落ち着き、一定した呼吸に変わった頃、ぽんと気安く肩を叩かれる。見上げた先には穏やかな笑みがあり、その中に二つの小さな月が朧に、どこか蒼みを帯びて光っている。口をぱくぱくと何度か開いて、三日月は山姥切の横に腰かけた。座るぞ、か何か言ったのだろう。特に拒む理由もない。
「……あの鬼は、あの刀を奪おうとしているのか」
あの鬼がこの他の場所を目指しているところを、山姥切は見たことがない。必ず鬼のぎょろりと飛び出た目玉の先には審神者の離れがあり、審神者は刀の残骸を抱え込んで泣いて拒んでいるように見える。しかし三日月はゆるやかに首を横に振った。
「だったら、あの審神者が引き付けているのか」
三日月は珍しく山姥切の言葉にどう答えるか迷っているように見えた。笑みはそのまま、しかし眉尻がやや下がっている。だが、三日月の言葉が聞こえない山姥切にとってそのためらいは無駄なものだ。いや、もういい、と話を変えることにした。元々この夜の庭で三日月にかける言葉のほとんどが独り言のようなものだ。
「あの月もお前がやっているのか」
夜空は夕暮れあたりから流れてきた重たげな暗雲で敷き詰められている。しかし中天のあたりには襤褸布に空いた穴のような隙間がぽつぽつ空いて、細い月の姿を見せたり隠したりする。記憶の限りでは今日は小望月くらいのはずだ。少なくとも暗雲の先をすっぱりと斬ってしまいそうな三日月ではない。
「お前が来ると、いつも三日月になる」
目を横に流したが、そこに笑みは無かった。代わりに、目をきょとんと丸めた不思議そうな顔があるだけだ。知らず体に力が入っていたらしい。気が抜けて背を丸める。表情から察するに、恐らく本人の意図したものではないのだろう。だが、この男が「境目」を超えた男で、何か世の理を覆すことをその身に従えていることは明らかだった。
「お前はどうやって黄泉路を辿っているんだ。誰でもできるのか」
言って、三日月の顔を見ないまま小さく笑った。そんなわけないな。そんなことができるなら、山姥切はこのどことも知れぬ不思議な本丸の離れ、その小さな濡れ縁に腰かけてなどいないだろう。では三日月と──「あいつ」は、何が違ったんだろうか。渡った時の長さだろうか。霊力の違いだろうか。あるいは一期一振という伴侶があるからか。
そもそも折れれば、刀剣男士はどこへ赴くのだろう。歴史修正主義者と戦うために集められた審神者は数千とも数万とも聞く。そのそれぞれに同じような「なり」をした刀剣男士が付き従っている。折れれば無に還るのか、大本のような場所へ帰るのか、それともこの三日月のようにどこか全く違う世へと移るのか。依代たる刀身が折れた時、その他に折れるものは一体なんなのだろう。
「……どう思う。折れた刀が打ち直されたら、それは同じ刀なのか」
三日月の青い狩衣の袖を掴み、目を合わせた。表情はまた穏やかな笑みに戻っていた。
「同じように話すし、同じように戦う。同じように物を食うし、同じように眠る……何もかも同じだよな」
ずっと考えてきた。呻きながら、苦しみながら頭を抱えてきた。しかし未だに答えらしきものはちらりとも見えてこない。そろそろ疲れてきていて、誰かに答えを与えてほしいと思う。だが与えられた答えに満足できないことももう随分前に知っていた。
「俺だけなんだ。俺だけ違うんだ」
どれだけ同じ名を持つ刀を見たって、見も知らぬ刀にしか見えない。
三日月の口が開いたか閉じたままなのかも確認しないまま、山姥切はまた布を引き寄せて顔を伏せた。隣に気配を感じながら、じっと夜が更ける静寂だけを聞いていた。
そっと、また肩に手が置かれた。ぽん、ぽんと何度かそれが繰り返される内に、拳の内に水気が染みた。するとまた大きな手は離れていった。不思議な男だと思う。何も気にかけず無邪気に振る舞っているように見えて、ものの加減を心得ている。
四
床に着いたのが何時だろうと朝はやってきて、その変わりない道理に慣れ切った体も早々に目覚めてしまう。最近は陽が少しでも顔を出した途端に夜気が熱気に取って変わるから尚のことだ。どこか重い頭を振りつつ、やっとのことで身支度を終える。「外」では長谷部も同じように陽光に合わせて活動していたのだろうか。大体似たような時間に目覚めて、山姥切の後を追うように身支度を終えている。
「どうした」
じっと見つめる視線に気づいたのか、長谷部は山姥切を振り返った。いつもの、何を考えているか分からないぼんやりとした表情だ。こうして廊下を並んで歩いていると、長谷部のほうがやや目線が高いのが分かる。体つきも山姥切が受けた人の身よりしっかりしているように見える。だというのにこいつは。
「……お前はどこへ行こうとしてるんだ」
「お前はどこへ行くんだ」
やはり今日も何も考えず山姥切の後を追っているだけらしい。重い頭を片手で支える。
「俺は石切丸の手伝いを頼まれている」
「そうか」
石切丸は、『清め』を本業とするこの本丸で中心的な存在だ。穢れ祓いに用いられる祈祷場でほぼ一日を過ごし、各本丸から託された刀たちの清めを担っている。祈祷場は常に掃き清められていなければならないものらしく、手が動かせるものは交代で朝一の清掃を手助けすることになっている。山姥切もその例に漏れない。
ところが、何故か長谷部はこの仕事を免除されている。と言うのも、石切丸が長谷部の顔を見るなり「君は入らないほうがいい」と気遣わしげに言ったためだ。長谷部もそれを何の疑問も差し挟まずに受け入れたようだった。そうすると横から山姥切がその理由を問うこともできなくなる。
山姥切が再び歩き出すと、長谷部もそれに続いた。じっとその横顔を眺めるとまた、どうしたと問われるも、どうしたもこうしたもない。
「……付いてくる気か」
「祈祷場の中に入らなければいいんだろう」
「それでお前は何をするんだ」
「分からん」
明快である。
仕方が無いので厨の手伝いをするよう頼むことにした。すると素直に頷いて離れていくのだから、これを自分から考えついてくれればいいのだが。どうにもここ数日、長谷部は前にも増して山姥切の後を追って行動するようになった気がする。しかし何がきっかけなのか山姥切には見当もつかないのだ。なぜ付いて来るのかと直接問うてみたりもした。すると、長谷部は珍しく困惑したような妙な表情で言う。何かを思い出しそうだから、と。
ぼんやりしているから忘れがちだが、長谷部もこの本丸の一期や三日月と並ぶくらい謎が多い男だ。審神者が出て行けと言うから出てきたと言うが、その審神者から酷な仕打ちを受けたわけでもないらしい。むしろ優しい言葉をかけられたようなことも言っていた。まさかあの性格のせいで審神者に匙ごと放り投げられたわけじゃないだろうな。
「寝不足かい?夜更けまで一体何をしていたのかな……なんてね」
そんなことをつらつらと考えつつ踏み入れた祈祷場、はたきを片手にあくびを噛み殺したところをばっちり見られたらしい。気配なく背後に立たれ、思わずがばりと体を翻してしまう。曇り空の隙間から降りる淡い陽光を窓から受けて、緑がかった鈍色の長髪が艶やかに光っている。この本丸で石切丸に付いて清めの手助けをしているにっかり青江だ。祈祷場の入り口には優しい笑みを浮かべる石切丸の顔も覗いている。
「いつもありがとう。山姥切さん」
もういいよ、朝餉に行っておいでと柔らかい声音で告げられ戸惑う。寝不足と言ってもほんの数刻床につくのが遅くなっただけの話だ。病じゃあるまいし、気遣われるほどではない。まだ祈祷場に軽くはたきをかけたくらいだから、とても充分掃除をしたとは言えないだろう。毎日どこよりも念入りに清められる場だ。だからこそ埃ひとつ舞ってはいないのも確かだが。
「……こんなものでいいのか」
「もちろんだよ。君はいつも仕事が丁寧だから気になるかな」
「仕上げは僕たちでやっているから安心していいよ」
「だが」
君も堅物だねえ、と黄金色の瞳にはどこか意味ありげな笑みが浮かぶ。この本丸の一期と似たような方向で、元の本丸に居た頃から山姥切はにっかり青江のこういう笑みと言い回しがあまり得意ではない。表情にそれが出てしまったのだろうか、石切丸と青江はくすくすと顔を見合わせて笑い始めてしまった。そうして笑っているとどこか幼げに見えるのも、どこの青江でも同じらしい。
「この場は山姥切さんが掃除をした。だから、『ここは清浄で曇るところなどない』と信じることができればそれでいいんだ」
「そういう意味では、『穢れ』も『清め』も同じようなものかもしれないねえ」
もらうよ、と流れるような仕草で手を差し出され、思わずはたきを青江に渡してしまった。分かりやすいようで一切掴めない言葉の連なりは、いつまで咀嚼しても飲み込むことができない。
「すまないが……よく、分からない」
こういう時に、何か自分に足りていないのではないか、欠けているのではないか──やはり俺は「写し」だからかと焦る気持ちが出てしまう。こればかりはいくら鍛錬しても消えなかった。布を掴み込む山姥切の姿はこの二振の目にはどう映ったのだろうか。石切丸がゆっくりと山姥切に近づいてぽんと山姥切の肩を叩く。ちょうど昨晩同じ場所を触れた感触によく似ていた。
「大切なことはね、納得することだと私は思っているよ」
納得。その言葉は山姥切にとっては随分遠くにあるものだ。それを探してこうして旅を続けてきた気がする。随分長くどことも知れぬ時を重苦しい気持ちで彷徨った。だが未だにその背のひとつも見えはしない。納得と、諦めと妥協と──「あいつ」への裏切りと。何が違うのか分からない。
「どうすれば、できるんだ」
「え?」
「どうすれば、『納得』できる」
顔を上げた先には石切丸のきょとんと開いた眦があった。しかしすぐにそれを和ませて、石切丸は優しい声で言った。朝餉に行きなさい。
しばらく呆然としてしまった。声音は優しいまま、笑みも柔らかいまま、あたたかい手のひらも肩に乗ったままだ。だが、ひどく突き放された気がして、山姥切はよろよろと後退した。自分が何故だか情けなくなり、肩を落として明るい祈祷場を出る。すごすごと薄暗い廊下を歩いていると軽い足音が近づいて来た。
「おやおや、追いついてしまったねぇ」
目だけを背後にちらりとやれば、青江だ。神饌を取りに行くよう石切丸に頼まれたらしい。今はとにかく一振になりたい気分だったので益々気分が沈む。俯いて布を引き寄せ歩く速度を早くしたが、青江もそれにひたとついて来る。
「そんなに縮こまって……力を抜いてごらんよ。恥ずかしがらずにさ」
「……放っておいてくれ」
「だけど後ろから見ているとまるで……ふふ、一反木綿みたいじゃないかい?」
「……一反、木綿?」
「そうそう、君みたいにこう……布を被っている物の怪さ」
「…………物の怪……」
じろりと振り返るが、愉快そうに笑っている青江に邪気は感じない。付喪神だって人間から見れば物の怪の一味のようなものには違いない。小さくため息をついてそれ以上の追求を止める。
「……詳しいのか」
「うん?」
「物の怪とか、そういうやつに」
「ああ……どうだろう。ただ僕には『そういう』来歴があるから、他より興味はあるかな?」
青江が口の端を吊り上げて艶やかに微笑むと、含みがひとつもふたつもありそうでやっぱり苦手だ。なるべく目は合わさないようにして口早に語って聞かせたのはあの女鬼のことだ。ぎょろりと剥き出した目。大きな口と不快な笑い声。ぼさぼさと水気の無い長い黒髪を両手で掴んでいる。相槌すら返さない青江が気になってちらりと目を後方へ遣れば、笑みを消して顎に長い指を当てている。
「見たのかい?その鬼を」
「いや……ただ、それが出る本丸の話を聞いたことがあるだけだ。最近ふと思い出した」
どこか切迫した雰囲気に、つい嘘をついてしまった。多くなってしまった口数にひやりと背が冷えたが、青江は勘繰る様子もなく目を伏せる。
「あまり考えないほうがいいよ。呼んでしまうといけないからね」
「悪いものなのか」
「うーん……話だけじゃなんとも言えないけど、多分それは『縊鬼』っていう鬼じゃないかな」
いつき、繰り返した山姥切にずいと顔を寄せ、青江は自分の首元に手を当ててにっかりと笑った。
「括らせたがるのさ。人の首をね」
思わず後退して柱に背をぶつけた山姥切をくすくす笑いながら青江は追い越して行く。正直後を追って歩くのも気が引けたが、同じ厨に向かっているのだから仕方ない。
「まあ、そういう意味では、縊鬼も僕たちも同じようなものかもしれないね」
先ほどの石切丸に向けた言葉をなぞったのだろうが、物騒さが全く違う。夜半の暗闇にぼうっと佇む離れを、その中ですすり泣いて暮らす女の姿を頭から振り払い振り払い、山姥切は大きくため息を吐き出した。
「……人の首を斬るのは人だろ」
「なるほどそうかもねえ」
案外やるね、と何故か誉められたが、正直全く嬉しくはなかった。
六
「いいね、草刈り。すかっとする!」
「オラオラオラオラァ!」
もう数度目ともなる「草刈り」に加州も大和守もすっかり慣れた様子だ。こちらはこの前敵が多く居ただとか、あちらは敵が隠れやすいだとか、半ば競うようにして自身を大いに振るっている。初日に大和守は軽傷を負ってしまったはずなのだが、それを庇う素振りすら見えない。錬度が上がれば多少の傷は気にならなくなるものである。しかし、ほとんど快癒しているとはいえ、今はどちらも「清めの本丸」で穢れ祓いを受けている身のはずなのだ。後衛を引き受けている御手杵もすっかり呆れた表情だ。
「長谷部、油断はするな」
「分かった」
今はまだ殊勝な表情で頷いているが、「こんな」長谷部でもやはり実戦では血が騒ぐらしい。少し目を離すとすぐ敵の只中へ突っ込んでは混戦になっている。おかげで錬度も順調に上がっているようだ。同時に生傷も絶えないはずなのだが、長谷部の場合、どういう仕組みか軽傷程度の傷は数刻もすれば消え去ってしまうのだった。「特別元気」の名は伊達ではない。審神者の霊力の質によって生じた特別変異では、というのが一期の見解だったが、あまり深堀りするとこの男が一振彷徨っていた理由に触れてしまいそうで、敢えて誰も踏み込もうとはしていない。
一期が山姥切たちに依頼したのは「里」に迷い込んだ敵の始末だ。演練の他に、時の政府は戦力強化のためいくつかの里を用意している。日頃は霊力に通じた人間たちがこの里を隠し、決まった間にだけここを審神者に開放している。ここで出てくる「敵」は、訓練用に術者が作り出したもので本物の敵ではない。しかし、刀剣男士が多く集うためか、そのような術が何か呼び水になってしまっているのか、閉ざされた里には度々本物の敵が迷い込んでくるようだ。巧妙に時の狭間に隠された里は、敵にとっては袋小路のようなもので、一度迷い込めば二度と抜け出すことはできない。図らずも里はねずみ捕りのような役目をも負う形になっているらしい。里では、数人の審神者が常駐し、そういった敵を任務の片手間に討っている。だが、ある里ではここのところ弱い敵が多くかかって切りがないから、少し加勢してくれという話が一期まで回ってきたのだ。
瘴気の強い敵ほど感知が容易く、里を守る本丸共同で早々に片づけてしまうので、残るは雑魚ばかりだという。敵と味方との境界も結界で明確に線引きされている。更には万一に備え、毎度必ず高錬度の後衛も付いている。病み上がりの刀たちにとっては絶好の肩慣らしというところだろう。今までも同じ依頼を受けてきた経緯があるらしく、「あの」一期にゆっくり休ませてももらえないんだってなあ、無理せず頼ってくれ、と山姥切たちを出迎えた御手杵は同情的だった。今やそれが無用の心配だったと悟っている様子だが。無論、貴方がたの主にも話は通っております。実戦に出ても新たに穢れを受けるところがないか、経過観察の意味もありまして。大丈夫ですよ、あちらにあるのは親交の深い刀ばかりですからな──などと滔々と和やかな笑みで語っていた「あの」一期の刃望のほどが知れる。
煙のように湿った薄霞の中、叢を駆け抜ける。中天にあるのはただただ灰色の雲だ。しかし雨の降りだす気配はあまり感じない。蒸した空気、遠くで数条立ち昇る蝉の鳴き声が、この里も夏を迎え入れつつあることを感じさせた。
連日、主に加州と大和守が猛然と狩りを続けているためだろう、日に日に敵の数が少なくなっていることを感じる。半刻ほどはいつものように散り散りになって敵と切り結んでいたが、一刻も経とうとする頃には戦場は静まり返ってしまっていた。どこから拾ってきたのか長い木の棒を手にした不満顔の加州は、それでざくざくと草を払いながら結界からより離れた場所を探っている。用心のためというよりは、敵を誘い出す意図のほうが強いらしい。
結界から離れ過ぎると、万一強敵が潜んでいた場合の撤退が困難になる。自然に加州を先頭に他の者も集まり、塊になって行動する形になった。
「そう言えばさ、知ってる?あの本丸の主」
一応警戒は続けているが、何の気配も捉えることはできていない。無言で叢を払う作業が退屈なのだろう、不意に加州が口を開く。
「主も療養してるんだって」
「噂だろ?」
「……どういうことだ」
あの本丸の主、と聞いて目に浮かぶのは刀の残骸を抱えてすすり泣く女の姿だ。確かに健康そうにはとても見えなかったが、床に伏せた様子もなかった。加州はしんがりのお手杵にちらりと目を遣って声を低くする。
「俺たち結構長くあそこに居たからさ、色々噂も聞いたんだよね」
「僕が聞いたのは別の噂。あそこの主は罪人なんだって。それで本丸から出られないようになってるってやつ」
何の罪だよ、と問われても、大和守はそこまで知らないよと素っ気ない。つい意識はまた夜に見た姿に戻ってしまう。蔵のように堅牢で人目に触れにくい離れと、そこから一歩も外へ出ようとしない審神者。枷や柵、結界など、囚われているような様子も無かったように思う。だが、加州の知る憶測も、大和守が伝え聞いた想像も、突飛と断ずることはできないことを山姥切だけが知っている。山姥切も何か聞いたか、そう問われて目が泳いだ。
「おっ、こんなところにも咲いてたんだなあ。見てみろ、これ、えーっとぉ、確か蝦夷紫って言うんだぞ」
「そうか。ここは蝦夷なのか」
「ん?ああ、そうか。そうかもなぁ」
幸い、加州たちの話は微塵も御手杵の耳には入っていなかったらしい。のんびりと間延びした声と、長谷部のとぼけた言葉になんだかどっと気が抜ける。戦場に立つといかにも「へし切長谷部らしく」敵に斬りかかっていくのだが、刃を納めた途端にこれだ。
「この話やめよっか。主が何であれ俺たちはお世話になってるんだし」
「お前が言い出したんだろ?」
「そうね。悪い悪い」
加州や大和守も同じく脱力したらしく、話が流れたようでこっそりと安堵する。しかし、変わった話の矛先が山姥切に向くのは何故なのか。蝦夷とか言ってるけど放っといていいの、などとせっつかれても絶対に声をかけたりしないぞ。俺がたとえ写しでもだ。
「長谷部っ、!」
その時、先ほどの呑気な声とは真逆の鋭い声を御手杵が上げた。後方から潜んでいた敵が飛び出してきたらしい。最も錬度の低い長谷部を狙ったようだが、今では長谷部もそれなりに錬度を重ねている。腐っても打刀──という言葉は言い過ぎにしても、高錬度の御手杵よりも早く刃を抜き去り、敵よりも早く跳躍し、刃を振り下ろして着地すると敵はもう沈んでいた。
「『特別元気』、やったじゃん!特がついたよ!」
長谷部の体を燐光が包み、どこからともなく桜吹雪が駆け抜けて淡雪のように消えていく。遠い昔、山姥切もああして錬度を重ねた。あの時に感じた高揚感が鮮烈に蘇ってくる。「この」長谷部もさすがに喜ぶだろう──そう思って歩み寄ったが、長谷部はこちらに背を向けたまま微動だにしない。
「……長谷部?」
返事すらない。近づく度わずかに肩が震えているのが分かった。不審に思って正面に回ると、刃を納めることすらせず、だらりと腕を垂らし、どこか呆然と明後日を眺め──長谷部は泣いていた。
「……主」
うわ言のように主、主と何度か繰り返し、頬を拭うこともしないまま、長谷部は己の胸に左手を当て、山姥切の向こうのどこかへと首を深く垂れた。
「主、ありがとうございます」